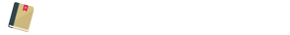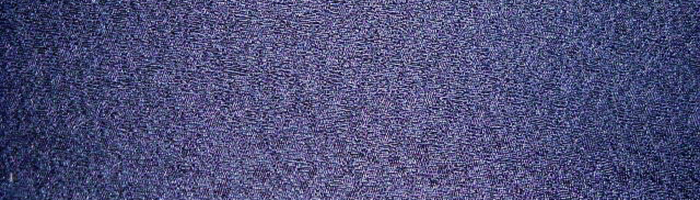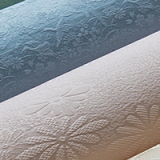紫系の伝統色
日本では紫色が古代より特別な意味を持っていました。聖徳太子の活躍した時代になりますが、冠位に合わせて色が定められ、その最上位の地位を象徴したのが紫色です。
- 紫色
- 葡萄色
- 藤色
- 二藍
- 滅紫
- 菫色
紫草の根から抽出された染液を使って紫色に染めます。江戸時代に京紫と呼ばれる色と江戸紫と呼ばれる色が使われていました。京紫は赤みの紫で、江戸紫は青みの紫ともいわれています。
葡萄色は、赤みがかった紫色になります。秋の深まりにともない葡萄の実も黒ずんだ紫色に熟し、その搾った汁も同じような色をするため、この名がつきました。王朝人にも好まれた色の一つになり、「枕草子」や「源氏物語」にも登場します。
藤は、私たち日本人にとってとてもなじみ深い花木になり、春の終わり頃から淡い紫色の花房をたらします。藤色は淡い青みのある花の色を指します。蓼藍と紅花を使うこともありますが、藤色は紫根を使い染めて椿灰で発色させていきます。
この二藍とは、藍と紅花を組み合わせて染めた紫色のことをいいますが、「二種類の藍を使い染めたもの」という意味があります。それぞれ染料の濃度によって微妙に色彩が異なってきて、赤みが強い二藍や青みが強い二藍など、その色彩は様々です。
鮮やかな紫色から、艶やかさや華やかさを取り去り、くすんだ灰色がかった色合いが滅紫の特徴になります。紫色に染めた後、染液を一晩放置することで紫色の色素が分解され鼠色がかってきます。
菫色は、日本に古くからある和菫の色になり、色としては、やや濃いめの紫色になります。「万葉集」の歌にありますが、春の野にすみれ採みにと来しわれそ野をなつかしみ一夜寝にけるとあり、摘まれるところから「ツミレ」「スミレ」となったとの説もあります。紫根で繰り返し染めます。
紫色ができるまで
材料になる紫草の根を掘り起こします。ちなみにこの根をシコンと呼び、紫根という字を書きます。根の長さは平均すると30cmほどになりますが、太い主根があり、そこに毛根が密生しています。根についている土を水を使って綺麗に洗い、乾燥させていきます。
乾燥させた根を長期間保存すると質が低下してしまいますので、根を掘り出し染めるまでの時間が、短ければ短いほどよい色に染まります。
乾燥させた根をお湯につけて、色素を抽出していきます。次に、お湯で柔らかくなった根を石臼に入れて、杵を使い徹底的につき砕いてつぶしていきます。
麻袋につぶした根の塊を詰めて、口をしっかり結び、約55度のお湯で満たした水槽に麻袋を入れて、手でもみます。圧力や熱、摩擦によって少しずつ色素が湯の中に出てきます。色を出し切ったら、再び根を石臼に戻して、杵でつぶします。この作業を三回ほど繰り返して、根から色素を抽出します。
椿の枝葉を燃やして作った灰汁を希釈して紫根の媒染に使います。この媒染剤を使うことで紫色を定着させます。
染料ができましたら、いよいよ染めていきます。布を紫色の液の中に入れて染めていきますが、最初のうちは、ほとんど色がつきません。この布を水洗いした後に媒染液の中に入れますと、初めて紫色に発色します。アルミニウム塩が椿の灰汁には含まれています。このアルミニウム塩が繊維に対して色を定着させる働きをします。ただし、美しい紫色を出すためには、染め重ねていくことが必要になります。
白い糸を染めるときにも、布と同様になります。紫根の色素は壊れやすいので、染め液をできるだけ早く使わなければなりません。濃い色にするには、繰り返し染めて重ねていかなければなりませんので、紫という色は染色技術の中でも、最も手間がかかります。紫色が高価になるのは、このような複雑な工程を経て染められるからです。